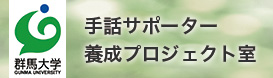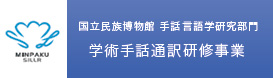ここでは,複合語を表出する際に留意点について,良い例と悪い例を比較しながら見ていただきます。
なお,悪い例は,良い例との違いがわかりやすいようにするため,あえてそのように表出しています。
1.脱落がないようにする
「逆ポーランド記法」の手話表現における構成要素は「逆」「ポーランド」「記(す)」「(方)法」から成り立っていますが,悪い例では「記(す)」が脱落してしまっています。手話表現における構成要素数が多くなるに連れてこうした脱落が生じやすくなりますので,事前準備の中で,専門用語をしっかり頭に入れて正確に手話で表出できるように練習をしておいてください。また,こうした専門用語はそのコンテクストにおいてキーワードとして何度も現れることがあります。2回目以降はいくつかの構成要素をあえて省略して短縮化させてもかまいません。ただしその場合でも省略する部分は一貫して同じになるようにしないと,通訳の受け手には同じ語と認識されにくく,わかりにくい通訳になってしまいます。
2.うなずきを入れない
複合語の場合には,構成要素間にうなずきを入れないようにする必要があります。
名詞Aと名詞Bの間にうなずきが入った場合には,「AとB」を意味する並列関係が表現されます。例1の「ジスルフィド結合」の悪い例は,「ジスルとフィドと結合」といったように読み取れてしまいます。
言いよどみであるポーズ,すなわち手の動きの停滞の場合には,語の切れ目とは認識されませんが,その場合でも,頭部の前傾が見られると構成要素の結合を妨げるので,理解を妨げる要因の一つになっています。
悪い例にみられるようなうなずきは,聞き慣れない言葉を聞いて訳出しようとするときに無意識的に短く区切って頭に入れようとしたり表出したりしてしまい,その短い区切りの単位に合わせて表出しながらついついうなずいてしまうというふうに考えられます。これを防ぐには,事前準備の中で専門用語をしっかり頭に入れて,なめらかに手話表出できるように練習をしておくことがポイントです。
3.音声の発話リズムに手の動きが連動しないようにする
音声日本語の発話リズムと手の動きが連動し,音声発話のフットに合わせて手の動きが反復される表現となって現れると,手話のもつリズムが崩れるため,各構成要素の持つ意味がとりづらくなったり,構成要素と構成要素の結合が不自然なものとなります。
上記の例では,「一致」という手話表現が,音声日本語では2フットですが,日本手話では1フットで表現することに注意が必要です。
4.複合語の構成要素同士の接続をなめらかにする
「所有権保護」という複合語の手話表現は,「所有」「権(利)」「保護」の3つの構成要素から成り立っています。これらを別々の単語ではなく「所有権保護」という複合語として表現するには,それぞれの構成要素の表出の後に手の動きの弱化が生じます(⇒保持の消失)。悪い例では,この手の動きの弱化がないため,通訳の受け手には「所有権」「保護」と別々の語に認識されやすく,わかりにくくなってしまっています。専門用語がスッと出てくるように頭に入れておく,手話で専門用語を表出する練習を事前に積んでおくといった対応策をとることで,手話表現の構成要素と構成要素の接続は意識しなくてもなめらかにつながり,手の動きの弱化が生じます。
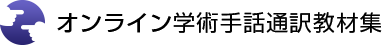
 新規登録
新規登録 会員専用
会員専用