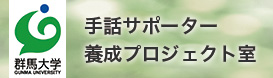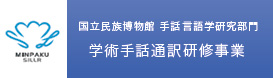例えば「長いこと難儀をかけた人じゃの」。「長き」とかっていうんじゃなくて「長い」って書いてますね。それから,「ござる」がいっぱい出てきますね。それから,「じゃ」が出てきますね。「難儀をかけた人じゃの」っていうふうにね。
【国語学入門:日本語の歴史(鎌倉・室町)―能・狂言】
39:54~40:16
手話にない表現がたくさん出てきますが,借用においては,起点テクストの元の表現のまま伝えるべき部分はどこかをよく考える必要があります。モデル通訳では,「長い(き)」の「長」,「難儀をかける」は手話単語を使い,「長き」,「ござる」,「じゃの」は指文字で表すことによって,室町時代の話し言葉の日本語の特徴が明確に伝わるようになっています。
また専門用語は,そのコンテクストにおいてキーワードでもあり,何度も繰り返し起点テクストに現れることが多くあります。その際,手話や指文字の使い分けが統一されておらず,表出するたびに表現が異なると,通訳の受け手には同じ語として認識されにくくわかりにくくなってしまいます。専門用語についてはあらかじめ,表現方法を決めておくようにしましょう。一語が長いものや複合語では,初出のみすべて表し,2回目以降は省略形で表すことが多くなりますが,省略の仕方についても,同様に表出のたびに表現が異ならないようにします。
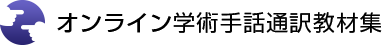
 新規登録
新規登録 会員専用
会員専用