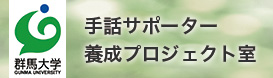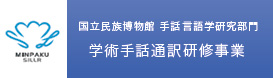小胞体に入ったたんぱく質は,合成されながらこういうことが起こる。合成されながら,大きく分けて,2つの出来事が起こります。1つは,ジスルフィド結合っていって,アミノ酸の中で,システインていうのは硫黄の残基を持つんですね,システインとシステインが酸化されてHがとれると,SS結合っていうのができるんですけど,すごくたんぱく質が折りたたまれるときに大事なことで,細胞質のたんぱく質は,ほとんど細胞質っていうのは基本プロトンが,OH基が多くて,還元状態なんですね。だから,SSの結合ができるってことは,細胞質は還元的環境なので,基本ジスルフィドはできません。だから,たんぱく質は基本ほどけた状態なんですけれども…
【生物科学概論:ミトコンドリアと葉緑体におけるエネルギー生産/細胞内区画と細胞内輸送】
11:34~12:30
学術手話通訳では,専門用語を借用表現によって起点言語のまま直訳的に表出します。借用表現でよく用いられるのは,指文字とマウジングです。コミュニティ通訳に比べて指文字が多用される傾向にありますので,指文字はスムーズによどみなく出せるように練習をしてください。専門用語は論旨を理解するためのキーワードとなっていることが多いので,通訳の受け手にしっかり伝わるように少し表出速度を落とすようにします。特に語の起点と終点の動きを弱化させず,しっかり止めるようにしてください。そして,起点言語からの借用であることが伝わるように目線の変化や見開きもしくは細め,軽いうなずき等のNMも手指とともに出すようにします。マウンジングも他の部分に比べてよりはっきりと行います。手話単語と指文字の使い分けについては,「専門用語の訳出 (2)手話単語と指文字の適切な使い分け」をご覧ください。
また,学術手話通訳のユーザーのろう者は,その専門分野を知悉している研究者や高等教育として当該学問分野を学ぶ学生です。専門用語を使うからこそ,短い表現ややりとりで言葉に出ない概念的なことも含めてその内容を適切に理解できます。そのため,専門用語を安易に別の言葉や表現に置き換えて訳出しないでください。
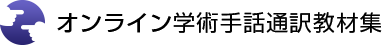
 新規登録
新規登録 会員専用
会員専用